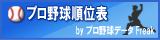先日、ボークと反則投球(←ココをクリック)について取り上げたのですが、もう少し掘り下げてみたいと思います。色々なボークがあるので、拙い文章よりも実際の動きで知ってもらった方が良いと感じます。この動画ですが、どこかで審判をされている方が編集された様です…
さてボークには、打者に対する反則と、走者に対する反則があることは、以前の投稿でご説明しました。今回は、後者である、走者に対する反則(牽制球)への補足です。
きっかけは、先日のU-18決勝戦で起きたあるプレーです。5回裏の攻撃でオコエ選手が出塁しますが、1塁で牽制アウトになります。あのシーンをTVで観た時は、息子も嫁さんも「あれ、ボークだよね?」とこぼしていました。確かに、際どいプレーでした。この時、息子にボークと取られなかった理由を聞かれたものの、TV中継は基本的にセンターから映像のため、納得の行く説明ができず終いでした。しかし、気になって仕方がなかったため、数日待ってYouTubeから1塁側から撮影された画像を探し当て、じっくり観察してみました。その結果、「ボークではない」ことが判明しました。
それはなぜなのか、まず公認野球規則を覗いてみます。
【8・05】塁にランナーがいるときは、次の場合ボークとなる。
(a)投手板に触れているピッチャーが投球に関連する動作を起こしながら投球を中止した場合。
「原注」左投げ、右投げ、いずれのピッチャーでも自由な足を振って投手板の後縁を越えたらバッターへ投球しなければならない。ただし、2塁ランナーのピックオフプレイのために2塁へ送球することは許される。
この「投手板の後縁」というのがミソです。左投手の場合、セットポジションの体勢を取った時には、正面に1塁が視界に入ります。つまり、1塁手もランナーも1塁塁審も、投手の自由な脚である、右脚の動きが良く見える訳です。
右脚が軸足である左脚とクロスすると、投球動作に入ると思いがちですが、投手板の後縁を越えていなければ、牽制球を投じてもボークにはなりません。この左投手のフォームの様に、極端な脚のねじれを使わずに、右脚を上げるのであれば、牽制なのか投球なのかの見分けが難しくなります。ボークは、打者やランナーを欺くことを防ぐ目的で設けられたルールと言われています。しかしこのプレーは、国際ルールが違う訳でもなく、1塁審判が見逃したのでもなく、ルールすれすれの動作で牽制球を投げられる「投手のテクニックが凄かった」と言うことなのです。
ですから、両脚がクロスするとボークというのは間違いです。それを知った上で、もう一度動画をご覧ください。
松岡修造さんに言わせれば、「これが世界に通用するプレーなんだ!」となるのでしょうか…