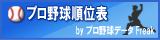このBlogで、インフィールドフライが発端でゲームセットに至る動画をご紹介しましたが、
先日の試合で同じ様なプレーが起こりました。広島カープは、9回に1死満塁とサヨナラのチャンスを作ります。ここで先発大瀬良大地投手の代打に小窪哲也選手が打席に入ります。スコット・マシソン投手は内野フライに打ち取り、3塁塁審が「インフィールドフライ」をコール(0分56秒あたり)します。しかし、サードを守る村田選手とファーストを守るフランシスコ選手がお見合いで捕球できず、ボールがフェアグランドに弾んでしまうのですが、フランシスコ選手がボールを持ち、本塁を踏んだ後一塁に送球します。その間に三塁走者の野間選手がホームを駆け抜けます。ただ、小窪選手がインフィールドフライでアウトとなっており、3塁走者をアウトにするにはタッチプレーが必要だったため、生還が認められました。
場内には責任審判員から説明があり、広島のサヨナラ勝ちがアナウンスされます(6分18秒あたり)。
球審もしくは塁審が「インフィールドフライ」を宣告した時点で、打者はアウトとなります。塁上の走者はフォースの状態が解除されると同時に、進塁義務もなくなります。そのため、捕手が本塁に触球して(ボールを持ったまま踏んで)も三塁走者はフォースアウトにはなりません。ですから野手は捕球した時点で、本塁を踏んで一塁に送球するのではなく、三塁から走ってきた走者にタッチ(触球)すれば、打者走者と三塁走者の併殺で、そのイニングを終了することができました。
ではここで、例を挙げてみます。ワンアウト満塁の場面で、意地悪なセカンドが「容易に捕球できる」はずのインフィールドフライをわざと自分の目の前に落したとします。3塁ランナーだったら、どうしますか?
– 3塁へ戻りますか?
– 塁が詰まっているのだから、ホームへ向かいますか?
ルール上は、「ボールインプレイであるから、通常の飛球と同様に走者は捕球の危険をわきまえて進塁してもよい。捕球された場合は、走者はリタッチ(再度の触塁)をして進塁することができる…」と書かれています。つまり、インフィールドフライが宣告されると打者は自動的にアウトですが、飛球が捕らえられていないので、リタッチの義務が不要となるのです。つまり、プレーは続くのですが、打者がアウトですから、ランナーは押し出されることはなく、進塁の義務もありません。
本塁へ向かうのは自由ですが、そのかわりにタッチアウトになる危険があります。ランナーを混乱させようとして、わざとフライを捕らなかったセカンドのプレーに、まんまとはまってしまうことになるのです。また、本塁に向かわないまでも、「インフィールドフライだからボールデッド」と勘違いをし、塁を大きく離れてうっかりしていると、セカンドからの送球とタッチでアウトになる可能性があります。繰り返しとなりますが、インフィールドフライはボールインプレイです。ノーアウトかワンアウトで1、2塁、あるいは満塁で、インフィールドフライが上がった場合、ランナーは自分の塁に戻ってじっとしているのが安全な様がします。
さて、広島戦のシーンに戻ります。今回面白いと感じたのは、「インフィールドフライ」を球審から宣告したわけではないため、ボールを追い掛けたきた野手4人(内2人は外国人)は、恐らく「フォースプレー」と判断したのだと想像します。事実、球審はしばらくの間「アウト」の合図を続けていました。個人的には、一番飛球に近い位置にいた球審がコールすべきだったのではと考えます。
(後日追記:)このシーンをプロ野球ニュースの解説者達が判りやすく説明しています。
色々な意味で、今後に役立てたいと思います…