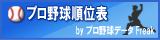先日のグランド練習で、普段別のポジションを守る選手達へファーストに廻ってもらい、ショートからの送球を受けるという練習をしていました。
ノッカー役のヘッドコーチの意図は色々あった様です。その一つに、無我夢中でファーストに投げていた彼らにとって、どんな送球でも捕球をしなければならないファーストの大変さを説いておりました。さて、ファーストというポジションには、ランナーが1塁にいる時、ピッチャーから牽制球を受け、ランナーにタッチするという役割があります。拙の息子は、学童最終学年でファーストを守ることが多く、やり始めの頃はランナーがいる時の立ち方について、審判から指導を受けることがありました。
ご紹介する動画は、ランナーの松本哲也選手にスポッットが当たっているのですが、あえてファーストを守る新井貴浩選手の足元に注目してください。
「牽制球に備える時は、ベースをまたがない様に」というのは、審判講習会を通じて教わるのですが、野球規則ではピンポイントでこれを禁ずると書かれてはいません。
しかし、この部分を読むと納得ができます。
【公認野球規則5.02 『守備位置』】 (旧4.03『試合開始』)
試合開始のとき、または試合中ボールインプレーになるときは、キャッチャーを除くすべての野手はフェア地域にいなければならない。
(c)ピッチャーとキャッチャーを除く各野手はフェア地域ならばどこに位置しても差し支えない。
「注」ピッチャーがバッターに投球する前に、キャッチャー以外の野手がファウル地域に位置を占めることは本条で禁止されているが、これに違反した場合のペナルティはない。審判員がこのような事態を発見した場合には、速やかに警告してフェア地域に戻らせた上、競技を続行しなければならないが、もし警告の余裕がなくそのままプレイが行われた場合でも、この反則行為があったからといってすべての行為を無効としないでその反則行為によって守備側が利益を得たと認められたときだけ、そのプレイは無効とする。
ベースをまたぐ後ろ脚は右脚になりますが、何も知らない選手に「ベースをまたいで」とだけ伝えた場合、彼らの右脚はファールゾーンに位置するはずです。器用にフェアゾーンに置くこともできますが、ランナーの帰塁の時に邪魔なるだけでなく、ブロック(走塁妨害)したとみなされます。実際にやってみると判りますが、両脚をフェアゾーンに置いた状態で、牽制球を待つためにはキツい体制を強いられます。
後ろ脚となる右脚は、ピッチャー寄りのベース角に置く様にしましょう…