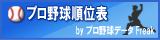この週末は、息子の大会とOP戦に帯同してきました。OP戦では、試合運びのテンポというのが、どこから生まれるのだろうかと、何が鍵になるのかを球場外から探っておりました。
その1つとして、投球テンポを挙げてみます。
ランナーがいない場面、またはランナーが1塁もしくは2塁にいる場面でのピッチャーの仕草が、次への投球までの時間を大きく左右します。特に球審で感じる事は、ランナーがいる・いないに関わらず、ボールをキャッチャーからボールを受け取って、投手プレートを踏んだら、まずはキャッチャーを観てほしいんですね。前の投球がファールでプレイが止まっている場合、塁上のランナーを牽制してもアウトにはできない時間帯なのに、チラチラ観る投手がいます。キャッチャーやショートからのサインには、牽制も含まれるでしょうが、特に静止した状態で、首だけの動きだけが許されているセットポジションで7秒以上静止したままでいると、脳科学的にも思う様な動きができなくなると言われています。投球テンポの良さ・速さという意味では、読売ジャイアンツに復帰した上原浩治投手が参考になると思います。
彼は、ランナーがいない場面では、ボールを受け取ってから4秒程度で投球モーションに入っています。このテンポは、守る野手のリズムをも生み出します。ランナーがいる場面で、ピンチを背負った時などは、投げ急ぎを防ぐために間合いを取る必要もあるでしょう。ですが、大したピンチでもない場面から1球毎にそれをやり続けてしまえば、守備のテンポも遅くなります。キャッチャーが出すサインや両手を使ったジェスチャーを観る、つまり投げるべき相手との会話をしてから、次への投球に備えてもらえたらと思います。
まぁ、拙の独り言なんですけどね…