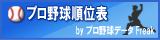拙が通勤途中に読んでいるネット記事の一つに、”sportiva(スポルティーバ)“というサイトがあります。先週末、「人生をかえたスポーツ漫画」というテーマで、MLBを含む現役プロ野球選手100人を対象にしたアンケート結果が掲載されていました。全員が全員、野球漫画に夢中になったのではなく、「スラムダンク」などの他の球技を題材にした漫画を好んだ選手もいて、なぜだか少し安心しました。
ただ、ある選手のコメントがすごく気になり、今回ここで取り上げます。正直、最初目にしたときは編集記者の誤記かと思った程です。
「僕は漫画大好きですよ。スポーツ漫画ですか? 影響を受けたのは『タッチ』ですね。その中で、上杉達也がアメリカで投げる『タッチ CROSS ROAD~風のゆくえ』というテレビ映画があったんです。見たのは中学生の時で、その頃、僕はピッチャーをあきらめていたんです。遠投は50メートルもいかないし、球速も80キロぐらいでしたから。バッティングは良かったので、打者としてやっていこうかなと。そんな時に見たのがタッチの映画だったんです。上杉達也はもともと真っすぐだけで、変化球は投げなかったのに、ピッチャーとしてアメリカで成功するためにフォークボールを覚えるんです。そういうピッチャーに対する一途な思いに感動して、もう一度ピッチャーをやろうと決めたんです。あれを見たおかげで、今の自分があるかもしれないですね」
これは、西武ライオンズ高橋朋己投手が懐述したコメントなのですが、なにか気が付きませんか?
「遠投は50メートルもいかないし、球速も80キロぐらい」というくだりです。しかも中学生… 遠投の距離といい、球速といい、実は小学4~5年生クラスの実力なのです。一説には、学年(小学生の場合)×10mが一般的な遠投距離だそうですから、ここで仮に「中学1年生の時の記録」として読み直しても、学童野球を経験してきた選手の運動能力としては「平均以下」だと想像します。
2012年ドラフト会議で、西濃運輸から埼玉西武ライオンズに4位指名を受け入団した高橋投手は、翌年ドラフト指名前から抱えていた左肩の不安・リハビリによりシーズン中盤まではファーム(2軍)での登板もなかったそうです。しかし、不安が癒えた後に数週間で一軍に昇格すると、ストレートの球威と高い奪三振率を武器に貴重な左の中継ぎとして活躍し、同年のレギュラーシーズン最終戦ではプロ初勝利を挙げました。
シーズン開幕前には、解説者の工藤元投手が「今年のイチ押し選手」として、彼を取り上げておりました。
「遠投は50メートルもいかないし、球速も80キロぐらい」というコメントは、実際本当らしいです。彼の球歴は、「小学2年から野球を始め、中学時代は三島田方シニアに所属した」となっていますので、恐らく中学で硬式に転向したのでは?と想像します。高校入学時点で、まだ98km程度だった球速は、高校3年生でようやく129kmに達します。高校時代は、故障の影響もありエースにはなれず、所属チームとしても静岡県予選3回戦で5回コールド負けを喫したため、甲子園出場経験はありません。しかし、大学野球に向けて練習していた際に、当時の監督から腹筋・背筋を鍛えるために暖房用の薪割りを薦められ、2~3時間の作業を毎日続けたことで彼の人生は一変します。この筋力トレーニングが着実に実を結び、大学2年生の秋にベストナイン、3年生の春に最優秀投手賞を受賞。大学卒業後は西濃運輸に入社し、1年目となる2011年の春から公式戦に登板するまでに成長しました。プロ入り後は、サイドスローに近いスリークォーターから平均球速143km、最速149kmのストレートを武器に、2014年シーズンでは開幕から中継ぎとして登板し、配置転換からクローザーに抜擢されるまでに飛躍を遂げています。
中学時代の記録から察すると、小学生時代は少なくとも「野球で注目される選手ではなかった」はずです。また、学童時代に所属したチームに多くの同級生がいて、そこそこの強さであったならば、最高学年になってもレギュラーの当確ラインを彷徨い、決して思うような活躍ができる選手ではなかったと想像します。しかし、プロの世界に辿り付けたのは、「野球を続ける」気持ちが人一倍強かったこと、薪割りトレーニングを徹底的に実践したことが大きかったのでしょう。
以前、
で一度触れましたが、学童(小学生)や中学野球では、食事の摂取量や成長スピードの違いがあり、どうしても身体能力的な差が付きまとう時期です。高校生までに突出した成績を残せなくても、取り組み方次第で「プロ野球選手になれる」ことを、高橋投手が証明してみせてくれました。
学童野球チームに所属していても、「最高学年になれば、いつでも試合に出られる」保証はありません。お勉強も同様に、塾に通いさえすれば、「志望する私立中学に合格できる」保証はありません。少なくとも、決められた枠よりも多い人数が集まれば、その中から競争に勝ち残るための努力は、やはり求められてしまいます。小学生であっても、何らかの目標を立てたら、そこへ向けた日々の努力の大切さを、まず学ぶ必要があると個人的には考えます。何かに取り組み始めた小学生自身と周囲の大人は、できるだけ短期間に成長の実感を求めたり、運動神経の良し悪しで限界を決めつけてしまったり、子供の能力をつい周囲と比較して一喜一憂してしまいがちですが、「ゴール(目標)をいくつ達成したか」よりも、「どれだけ徹底して取り組めるか」を大切にするべきかなと改めて感じました。体作りに薪割りが良いのかはともかく、毎日2~3時間といえば、平日の部活に費やす時間と変わりませんから、彼は自分の将来のために、あえて野球から離れ、集中的にかつ徹底的に体を鍛えたのでしょうね。一人黙々とこなすという作業って、野球に限らず他のスポーツだったり、勉強にも通じるところがあります。
あ~、もう一度小学生の頃に戻りたいなぁ…