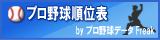先週末は、ドキドキ、ハラハラの春季大会第1戦でした。
さて、
「勝利・成功の秘訣」を物事に前向きな考えで臨むことだとしたら、ただ闇雲(やみくも)に、
「絶対に今日の試合はうまくいく!」
「自分は今よりも上手くなれる!」
といった気持ちを高めて終わるだけでなく、
「どうしたら今より上手くなれるかな?」
「今の状況をどう直せば活躍できるかな?」
と自分が置かれている環境や状況を振り返って、さらにその状況をよくするために、常に前向きな自問自答を繰り返すことが良いのだそうです。
実際に、高校野球やプロなどで活躍できる選手のインタビューを聞いても、自問自答を沢山重ねてきたことが伺えます。もし自問するチカラが身に付けば、「誰よりも早く上達できるのでは」と思ってしまいます。
ちなみに、自問自答を繰り返して答えを見つけ、行動するチカラを一般的には「自己解決能力」と呼ぶそうです。
今回ご紹介する動画ですが、元スピードスケーターでオリンピック金メダリストの清水宏保選手が、小学生に瞬発力を高める術を教える番組です。
面白いのは、最初から丁寧に「教える」ことはしていません。まず、どうしたらよいかを考えてもらい、悩んでいる生徒達に、時々アドバイスを送る程度です。
選手達は、彼らなりに練習中や試合後に自問自答をしていると思います。しかし、聞こえてくる彼らの発言のほとんどは、
「今日の試合は緊張しなかった!」
「今日のあの練習きつかったー!」
「今日は3打数2安打だった!」
「今日はエラーしなかった!」
と、感想だけを述べて「考える」ところまでは進まない様です。
ひとつひとつの練習やプレーに、
「なぜ監督は、あそこで僕にあのサインをだしたのだろう?」
「午後にやった、あの30分の練習にはどんな意味があるのだろう?」
などと「考える」ことはしていないと思います。
考えることが習慣になっていなかったのであれば、それは仕方がないことで、選手達にこの「考えるチカラ」を身につけさせるには、大人のサポートが必要の様な気がします。
試合後の反省会や、グランド練習時に、監督やヘッドコーチから、「質問」をする場面を目にします。面白いもので、質問をされたときに初めてその理由を考えようとするのが人間です。
子どものうちから「考えるチカラ」を育んでいれば、いつしかそれは習慣になり、人から問いかけられる前に、考えることができるようになります。
例えばですが、
「もしこのプレーをしたらどうなる?」
「じゃあ、このプレーができるようになるためにはどうすればいい?」
といった質問をして、発言(発表)する機会を設けることで、仮にどんな面白い言い訳を挙げたとしても、一度受け止めることで、彼らの発言への自信も付いていきます。
感じるチカラは知らず知らず身に付きますが、「考えるチカラ」はボールを捕る練習と同じで、何度も繰り返し働きかける必要があると思うのです。
「考えるチカラ」が身につけば、ひとつひとつのプレーから吸収できる量が増えます。
現時点での「考えるチカラ」を知るには、こんな実験(←ココをクリック)もあります。
今年も、彼らの成長ぶりが本当に楽しみです…