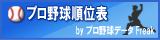試合に臨む選手にとって、スタメンに名前を連ねてもらえると、実際「何番を打つ」のかが次なる興味かと想像します。
打者としての憧れは、やはり4番ではないかなと。ただ、とにかく1回でも多く打席に立ちたいと思う小学生選手であれば、1番から3番あたりを希望するかもしれませんし、低学年になる程その気持ちの方が多かったりする様に見受けられます。
さて、チーム内での4番打者は、初回の攻撃でノーアウト満塁というビックイニングになり得る場面で、塁上の全選手(3人)をホームに返す枠割を担います。だから、この4番には長打力が、1番から3番の選手へは出塁率や走塁力が重んじられる傾向にあるわけです。時には、作戦としてヒッティングで出塁し、確実に先制点を奪いに行くため、走力と打率を重要視した打順を組むことがありますが、4番に座る選手は、基本的にその打順からは動かさない様です。
さて、なんでこんなテーマについて書いてみたかと言いますと、実はちょうど大相撲(5月場所)が開催されていることに気づき、さらに相撲界で横綱になることを「綱を張る」と表現されていることに、今更ながら疑問を抱いたわけです。野球界に目を向けると、どうでしょう? 特に読売ジャイアンツでは「4番を張る」という言い方が多用されているじゃないですか!
そこで、両者の違いが何なのかをまず想像してみました。すると、似たような両者ではあるのですが、決定的に異なる点が一つ思い浮かびます。それは、横綱に降格はありませんが、野球界の4番は結果次第で下位に落とされてしまうことです。打順はそのチームの監督が決めることとは言え、4番の座は実力と信頼で取り戻すことができます。相撲界では、降格=引退ですから、文字から察して最後の最後まで「張り続ける」ということになりますね。
相撲の歴史は、野球よりも長く、江戸時代にまで遡ります。相撲は、当時から興行として人気を博したそうで、最高位だった大関の中でも、より強い力士に横綱という称号を与えたのだとか。当時の横綱は、名誉的な意味合いが強かった様ですが、江戸時代だけで初代から12代までの横綱を輩出しています。その後、明治の時代に入ってから現在の地位が確立されたそうです。2014年の春場所で優勝した鶴竜(かくりゅう)は、第71代の横綱に昇進しました。血統を保持するわけでもなく、現在はモンゴル出身の力士ばかりが最高位に名前を連ねる時代です。それでも、世襲の様に表現されるのは、江戸幕府の将軍の様に力で支配する圧倒的な強さが込められているからだと想像します。考えてみれば、江戸時代は、260年あまりにわたって徳川将軍家が日本に君臨し、初代・家康から第15代・慶喜までが将軍を務め、世襲による後継ぎ(お世継ぎ)の混乱は、テレビドラマや本で色々な伝えられ方をされますが、どれもドロドロな話ばかりです。正室、側室が生んだ兄弟、「親戚」の御三家から養子を迎えるなど、壮絶な骨肉の争いがあったことは想像に難くないです。
学童野球では、体力的にも精神的にも、最高学年である6年生が「4番を張る」にふさわしい選手だと思いますし、怪我さえなければ一年間固定されることが望ましい。そこで、まず2014年初代4番打者に言いたいのは、最後まで4番を張り続けてほしいです。
でも、4番を張りたい選手が他に一人でもいるのであれば、遠慮せずにどんどん挑戦&アピールしてもらいたいです。試合に出ることにだけ満足せず、守備位置(ポジション)もそうなのですが、選手達にはもっと打順への拘りを持ってほしいんですね。
バントやスクイズ、走塁などは基本プレーとして重要です、そこは、スタメン選手全員ができる様に練習するのが当然だとしたら、バットを持つ以上、バッターボックスでフルスイングすることはもっと大切なことです。素振りはバントなどと違って、平日の時間を使えば幾らでも振り込めます。試合で打てなかったり、三振したのなら、次の週末までにもっとバットを振ってくるしかないと思います。その努力の延長上で繰り広げられる、「がっぷり四つ」の真剣勝負… そういう“骨肉の争い”なら、ベンチスタッフも歓迎してくれると思います。あと忘れずに言っておきますが、ドロドロになるのはユニフォームの方だけでお願いしますね。
ところで、打順で4番に就いた時、選手本人はどう読むのでしょうか? よんばんというか、よばんと読むか… 当たり前ですけど、野球であれば後者で呼んでもらわないといけませんけど。
まぁ、拙の独り言なんですけどね…