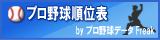メジャー・リーグでは、アンリトン・ルール(unwritten rules:ルールブックに書かれていないルール)と言われる暗黙の不文律(ルール)があるらしいです。例えば、派手なガッツポーズをしないとか、大差のついた試合でカウント3-0(3ボールノーストライク)から打たないとか、いずれも「モラルある行動」と表現し、大差のついたゲームの終盤でのバントや盗塁なども禁じているそうです。もし、それを無視して盗塁に成功しても、公式記録とならずに報復の死球が発生するのだとか。近年では、日本のプロ野球でもメジャーの影響を受けてなのか、この「暗黙のルール」の浸透が進み、しばしばトラブルとなるプレーがあったと言われています。
現在、甲子園では夏の高校野球が行われているのですが、どうもこの「暗黙のルール」を持ち出して、ネット上での書き込みやマスコミの論調が目に付きます。そもそも、プロ野球との決定的な違いは、高校野球の試合はトーナメント戦であり、負けてしまったら、その大会中のリベンジは果たせません。
例えば、「走るだけでは機動力。相手を嫌がらせるのが『破壊』」を意味する「機動破壊」をスローガンに持つ、群馬代表の健大高崎は、利府戦で計11盗塁を記録し、結果10-0で勝つのですが、8-0で迎えた8回2死からランナーが出塁すると、迷うことなく盗塁を決めてきました。
実際、大差のついた場面での盗塁に対して批判めいたコメントを目にしました。しかしですよ、健大高崎は地区予選で昨年の覇者である前橋育英を相手に、7回2アウトから6点をもぎとり、その後群馬県代表となって甲子園の切符を手にしました。
茨城代表の藤代は、1回戦の大垣日大戦で、初回に8点を奪いながらも、終盤ひっくり返されしまい10-12で敗退しました。高校野球においては、「終盤5点差以上」というセーフティリードが、あるようでないのが実際のところだと思います。
健大高崎が取り組んだ走塁は、勝ち抜くために選択した戦術です。「走る野球にスランプなし」という格言がある通り、甲子園では強豪相手にも怯まず、3回戦までに22盗塁を記録しました。つい先日、選手に走塁を教えたコーチのインタビュー記事を読んだのですが、興味深いコメントがありました。「走ればセーフになるという流れが一度できると、誰が走ってもセーフになっちゃう。相手もあきらめてきますからね。一度、50m8秒台の選手が三盗を成功させたこともありますが、そういう感じになってくるんです」だそうです。積み重ねた研究と練習の賜物があってこそですが、結局最後はメンタルなんだなと感じた次第です。
まぁ、拙の独り言なんですけどね…