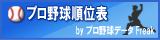今回は、広島カープ前田健(マエケン)投手を視察に来た、メージャーのスカウト達の目を釘付けにした選手を紹介します。
ネット記事はコチラ→マエケン視察の米スカウト釘付け 広島・菊池のポテンシャル(日刊ゲンダイ)
あるスカウトは「マエケン? そんなことより、キクチは何者なんだ?」と、こう言う。「あんなに守備範囲が広く、肩も強い日本人内野手は見たことがない。ファンタスティックな選手だ! 米国でも通用するかって…それはジョークかい? どの球団でも今すぐにレギュラーになれる。むしろ、キクチ以上の守備が出来る二塁手はメジャーにも5人といないだろう。キクチがFAを取るのはいつだ? ヒロシマはポスティングで彼を出す気はあるのか?」
ヒロシマのキクチとは、菊池涼介選手(二塁手)のことです。171cmと野球選手としては小柄ながら長打力もあり、さらにスローイングの正確さも備えた内野手です。一歩目の動き出しが非常に速く、中日ドラゴンズの谷繁元信は「グラウンドに犬が走っている」と評したそうです。捕球から送球まで機敏なことから、12球団のスカウトからは「守りでプロの飯が食える」と言わしめ、さらにはプロ入り後、仁志敏久や宮本慎也といった名手から守備範囲の広さを賞賛されています。他の二塁手が追いつけない打球にも追いついてしまうため、エラー(失策)が記録されることも多いのですが、その広い守備範囲からネット上の一部では「野生児」や「野人」と呼ばれています。その彼が、今年もトンデモナイ記録を樹立しました。それは、「2年連続500補殺以上」という数字です。野球ニュースで取り上げられる記録には、最多安打やホームラン王、最多勝にセーブ数などがありますが、500補殺という項目は大きく扱われません。単純計算で、1試合に4つ以上のアウトに絡んでいることになります。「セカンドゴロが4つあっただけじゃん」という感想で終わらせないで下さい。日本記録は、昨年菊池選手自らが樹立した528なのですが、9月30日のヤクルト戦でその記録を塗り替えてしまいました。
彼の守備をみると、「どこまでもボールを追いかけ、アウトにしようとする」その凄さに驚かされます。それでは、彼のプレーをご堪能ください。
以前このBlogでも触れましたが、宮本選手も「二塁手は強肩な方がよい」と言っておりました。あの守備範囲があっての補殺数樹立には、強肩があってこそだと納得してしまいました。
200本安打で表彰されるのなら、500補殺でも堂々表彰される価値があると感じたのは、拙だけでしょうか…