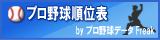イチロー選手が所属するマーリンズがブルワーズ戦に4−1で勝利した試合で、珍事が起きました。0ー0の2回、1アウトランナー1類の場面で、リアルミュート選手がセンター左に飛び込む今季第3号ホームランを放ったのですが、帰塁しようとした一塁ランナーのマルセル・オズナ選手を追い抜いたことでアウトとなり、シングル・ヒットでのタイムリーに判定が変更されました。つまり記録上は、リアルミュート選手のホームランはシングル・ヒットに変更され、オズナ選手の得点のみが認められた格好となります。
さて、そのシーンを観て気付いた事があります。リアルミュート選手が1塁を回ると、1、2塁間で打球を確認していたランナーのオズナ選手は、センター方向の深い打球にタッチアップしようとしたのか、ダッシュで1塁に帰塁します。その一方で、リアルミュート選手は打球の行方を目で追っていたため、オズナ選手の帰塁に気づかず、1塁ベースを回ったところで追い抜いたのだと感じました。
どちらのランナーが悪いのでしょうか? 個人的には、やはりバッター・ランナーの様な気がします。塁上のランナーは、フライとなる事を想定して、タッチアップに備えます。学童野球でもランナーが2塁・3塁にいたとしたら、そのランナー達はまずタッチアップに備えると考えられるからです。
いつか、「自分の打球を見届けると、前を行くランナーをも追い抜いてしまう可能性がある」という教材にしてみるか。
まぁ、拙の独り言なんですけどね…