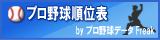この時期、学童野球は対外試合が禁じられているため、審判を務める機会がありません。
グラウンド練習では、ゲーム形式のシートノックだったり、ノックだったり、走塁練習をしてはいるので、立ち位置を確認する練習は可能です。どの位置からが1番観やすいか、選手達のプレーに目をやりながらも、つい考えてしまいます。この動画は、ある方が全く別の目的で編集されているのですが、塁審、特に1塁塁審の立ち位置が原因で、逆のジャッジをしている様に映ったので、記録として残しておきます。
1分3分辺りと、3分6秒辺りのプレーに注目してみました。特に、フォースプレーの場合は、少し離れて観た方が正しくジャッジできます。審判のジャッジに首を傾げる人達は、そこからかなり離れた場所から止まって観ています。つまり、近ければ良く見えるという事ではないのです。極端に近い場所から、また少し離れたところから同じプレーを観ると、視界というスクリーンに入ってくる映像は、際どいタイミング程、正反対に映る事があります。お父さんコーチに起こりがちな真逆の判定、それはプレーを観る立ち位置に問題があります。誤審の類を纏めた動画が数多く公開されているので、本来どの位置で観るべきかを少しずつ確認していこうかと考えています。
まぁ、拙の独り言なんですけどね…